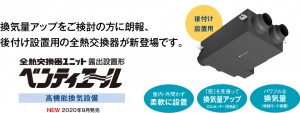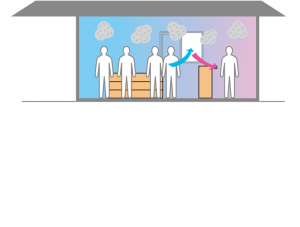経産省の概算要求は2021年度予算の概算要求額をとりまとめ公表したのをご存知でしょうか?
前回は環境省に関してのご紹介しましたが、
今回は環境省の21年度概算要求に関してご紹介していきます。
経済産業省の2021年度概算要求額
経済産業省の2021年度概算要求額は、2020年度当初予算額比12.7%増の1兆4335億円で、このうち、資源・エネルギー関係の概算要求額は、同比11.8%増の8365億円を計上した。再エネの主力電源化や工場・モビリティ等の省エネ化、水素社会の実現に向けた取り組みを支援するとともに、地域マイクログリッドの構築を支援する。
新規事業として、蓄電池等の地域分散電源等をより広域的な地域グリッドの需給調整等に活用するための制御技術等の実証事業に60.0億円を計上した。また、小規模で自立可能な電力系統網(地域マイクログリッド)の全国大での実装を支援(全国数十カ所)するため、2020年度当初予算額(17.3億円)比2.7倍となる46.8億円を計上した。
このほか、新規事業では、2020年3月に開所した世界最大級の再エネ由来水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」で製造した水素等を公共施設・駅・工場などに導入し実証等を実施する事業に78.5億円を計上。カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業に45.0億円を計上した。また、木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用に向けて、15.0億円を計上し、燃料材に適した早成樹・広葉樹等の調査・実証を行う。
制度的な取組では、再エネが主力電源として位置付けられるような「再エネ型の経済社会」を創造するため、市場価格をふまえて一定のプレミアムを交付する「FIP制度」の詳細検討や、基幹送電線利用ルールの見直し等を進める。また、2030年に向けて、非効率な石炭火力のフェードアウトを実現するための規制的手法のあり方等について検討を進める。
福島の着実な復興・再生」「イノベーションによる脱炭素化の推進」「社会環境の激変に対応した資源・エネルギー強靱化」の3つを柱とする、資源・エネルギー関係概算要求のポイントは上図を参照のこと。
再エネ主力電源化・省エネ化や水素社会実現、地域マイクログリッド構築に向けた概算要求額と施策の概要は以下の通り。数字は概算要求額(2020年度当初予算額)。
福島の着実な復興・再生 1234億円(932億円)
福島新エネ社会構想等の実現 569億円(462億円)
産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた水素社会モデル構築実証事業 78.5億円(新規)
H2Rでの実証の実施(水電解装置の耐久性の検証や制御システムの最適化等)や、製造した水素の先進導入 79(新規)
福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金 60億円(40億円)
福島県での再エネ導入拡大に向けた、発電設備(太陽光・風力発電計60万kW)や送電線(総延長80km)の導入支援、産総研福島再生可能エネルギー研究所における最先端の研究拠点化(車載向けの高効率かつ曲面形成できる太陽電池の開発等)
イノベーションによる脱炭素化の推進 5303億円(4617億円)
再エネ主力電源化・省エネの推進 2310億円(1988億円)
洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業 86.8億円(76.5億円)
洋上風力発電の導入拡大を目指した新規海域調査の実施(毎年100万kW程度を念頭に検討中)
太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業 36.0億円(30.0億円)
薄型・超軽量・長寿命等の太陽電池の技術開発(2030年頃までに建材用途パネルの 寿命2倍、重量1/4等)
木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業 15.0億円(新規)
国産木質バイオマス発電・熱利用の促進(未活用の早生樹等の活用実証。針葉樹の2.5倍の収穫量、育林費1/3)
先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 484.5億円(459.5億円の内数)
工場・事業場の電化等、先進的な省エネを重点支援(従来化石燃料を用いていたヒートポンプの電化等)
CCUS/カーボンリサイクルの推進 530億円(437億円)
カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業 45.0億円(新規)
バイオ由来製品を生産する微生物等の機能性向上を図るとともに、生産プロセスの共通基盤技術の確立等による低コスト化・高品質化を進め社会実装を図る
プラスチック有効利用高度化事業 16.0億円(10.0億円)
これまで国内で再資源化されていなかった廃プラスチックの有効利用・資源循環に関する技術の開発、海洋生分解性プラスチックの新素材の開発などを行う
水素社会実現の加速 848億円(700億円)
未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 74.8億円(141.2億円の内数)
国際的な水素サプライチェーンの実証(世界初の液化水素運搬船で豪州から水素を運搬)
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 200.0億円(130.0億円)
FCV等の次世代自動車の普及促進
社会環境の激変に対応した資源・エネルギー強靱化 4305億円(3719億円)
地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金 46.8億円(17.3億円)
地域分散や真の地産地消にも資する小規模で自立可能な電力系統網(地域マイクログリッド)の全国大での実装支援(全国数十カ所)
蓄電池等の分散型エネルギーシステムにおける次世代技術構築実証事業 60.0億円(新規)
蓄電池等の地域分散電源等をより広域的な地域グリッドの需給調整等に活用するための制御技術等の実証
まとめ
前回は環境省、今回は経済産業省の21年度概算要求に関してご紹介しました。
次回は農水省に関してご紹介します。