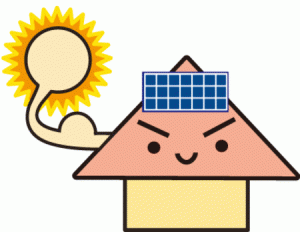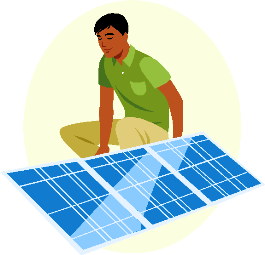皆さんは本日平成31年度の予算案が閣議決定されたのをご存知でしょうか?
経済産業省、環境省、国土交通省がそれぞれ再エネ・省エネに関する補助金制度に関して新しい情報を発信しています。
今回は各省庁が発表した再エネ・省エネに関する補助金を2回に渡ってご紹介していきます。まずは経済産業省、国土交通省の発表内容です。
経済産業省
エネルギー需給構造高度化対策 [エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定(石油石炭税財源)]
省エネルギー関連予算
オイルショック後並みの大幅なエネルギー消費効率の改善を目指すため、省エネルギー 技術の研究開発や規制的手法を推進しつつ、工場等における省エネ設備投資やクリーンエ ネルギー自動車の購入支援を行う。
省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 431.4 億円(30 当初 600.4 億円)
省エネ設備への入替促進に向けて、「工場・事業場単位」及び「設備単位」、「企業間連携の取組」 での支援を行う。
また、現行の ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)よりも省エネ率の高い ZEH+の導入を支援するほか、高性能断熱建材といった次世代省エネ建材の導入を支援する。
(注)電気需要の削減に資する設備投資に関する緊急対策等 (31 当初 臨時・特別の措置)
災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金 68.5億円(41.0億円)
需要家側のエネルギーリソース(蓄電池や電気自動車(EV)、発電設備、ディマンドリスポンス等)を IoT技術により、遠隔で統合制御し、あたかも一つの発電所(バーチャルパワープラント)のように機能 させ、電力の需給バランス調整に活用する技術の実証を行う。
- 災害による大規模停電の被害・リスク最小化のために、情報通信網、電灯、冷暖房等、国民の生活維 持に欠かせない最低限の電力エネルギーを需要家側で確保し、エネルギー供給源を分散化することで電 力レジリエンスを向上させることを目的とする。
国土交通省
豊かな暮らしの礎となる地域づくり
(1)都市機能の誘導・集約や持続可能な地域公共交通ネットワーク等の 実現による「コンパクト・プラス・ネットワーク」の推進。
(2)空き家や空き地等への対策を進めるとともに、地域の魅力や資源を 活かした、個性・活力のある地域を形成。
(3)多様なライフステージに対応した誰もが豊かに暮らせる住生活環境 の整備を促進。
省エネ住宅・建築物の普及 [533 億円(1.09)] ※計数については、一部重複がある
新築住宅・建築物の2020年度までの省エネルギー基準への段階的な適合や、 2030年 度の民生部門のCO₂削減目標の達成に向けて、省エネ住宅・建築物の普及を加速する。
・ 省エネ住宅・建築物の普及の加速に向けた中小住宅生産者等への支援体制の整備
・ 中小事業者の連携による省エネ性能に優れた木造住宅の整備・改修等への支援の強化
・ 先導的な省エネ建築物等の整備の促進や既存建築物等の省エネ改修等への支援の強化
・ CLT等や地域の気候風土に応じた木造建築技術を活用した先導的な取組に対する支援
・ IoT等の先導的な技術を活用した住宅等の実証的な取組に対する支援
・ 地域の木造住宅施工技術体制の強化に向けた大工技能者の育成・技術力向上への支援
まとめ
今回の経済産業省と国土交通省に関する平成31年度再エネ・省エネに関する補助金についてご紹介いたしました。次回は環境省に関してご紹介




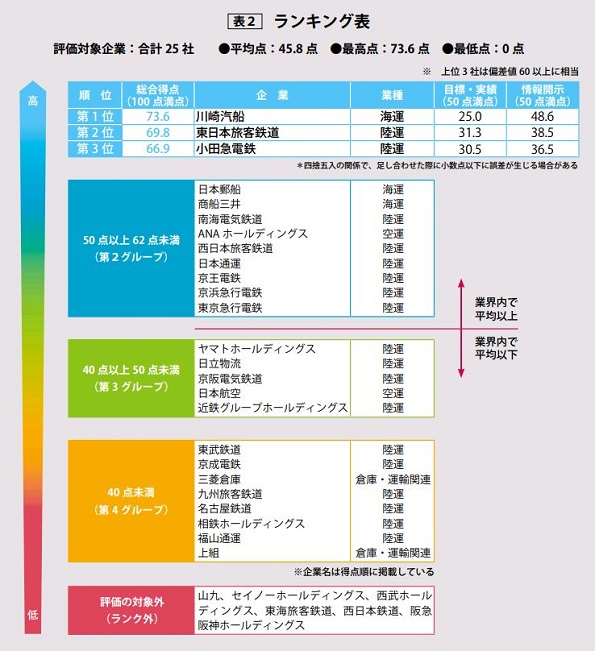
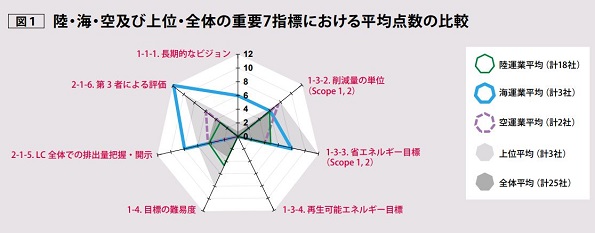

![20161216_a01[1]](http://e-sharing.sakura.ne.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/20161216_a0111.jpg)