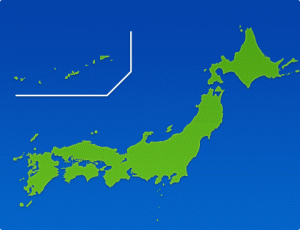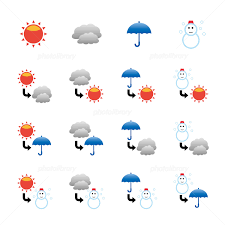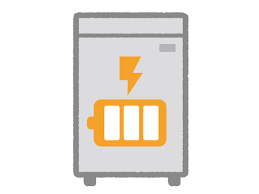今回は21年度FIT買取価格を決定に関しての発表があったので、こちらの内容についてご紹介していきます。

21年度FIT買取価格を決定
経済産業省は3月24日、固定価格買取制度(FIT制度)における2021年度の買取価格と、2021年度に電気の使用量に応じて需要家が負担する賦課金単価等を決定し公表した。
今回、調達価格等算定委員会の「令和3年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、太陽光発電、風力発電、一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料の買取価格等を決定した。それ以外の買取価格はこれまでに決定している。
住宅用太陽光(10kW未満)の買取価格は2020年度より2円下げ、19円/kWhとした。浮体式洋上風力発電と、一般木材等バイオマス発電(10,000kW未満)は、2020年度の買取価格を据え置き、その他は2020年度より1円下げた。また、2020年度に入札対象だった着床式洋上風力発電は入札を廃止し、買取価格を32円/kWhとした。
250kW以上の太陽光と、250kW以上の陸上風力発電は入札対象となり、事前に上限価格を公表して実施する。一般木材等バイオマス発電(10,000kW以上)・バイオマス液体燃料(全規模)の入札は、これまで通り上限価格を非公表で実施する。
2021年度の賦課金単価は3.36円/kWh(前年度2.98円/kWh)。買取価格を踏まえて算定した。1カ月の電力使用量が260kWhの家庭の平均モデルでみると、年額10,476円、月額873円の負担となる。このモデルの負担額は初めて1万円を突破した。2021年度の賦課金単価は、2021年5月検針分の電気料金から2022年4月検針分の電気料金まで適用される。
今回決定した、1kWh当たりの買取価格は下記の通り。
1kWh当たりの買取価格について
太陽光発電
電源 規模 (参考)2020年度 2021年度
住宅用(10kW未満) 10kW未満 21円 19円
事業用(10kW以上50kW未満)
(※)2020年度から、自家消費型の地域活用要件が設定されている。 10kW以上
50kW未満 13円+税 12円+税
事業用(50kW以上250kW未満) 50kW以上
250kW未満 12円+税 11円+税
事業用(250kW以上)
2021年度の買取価格は入札により決定。2021年度の入札回数は4回。上限価格は、それぞれ、11.00円(第8回)、10.75円(第9回)、10.50円(第10回)、10.25円(第11回)。
風力発電
電源 規模 (参考)2020年度 2021年度
陸上風力(250kW未満) 250kW未満 18円+税 17円+税
陸上風力(250kW以上)
2021年度の買取価格は入札により決定。2021年度の入札回数は1回。上限価格は、17.00円。
電源 規模 (参考)2020年度 2021年度
陸上風力(リプレース) 全規模 16円+税 15円+税
着床式洋上風力発電 全規模 入札 32円+税
浮体式洋上風力発電 全規模 36円+税 36円+税
一般木材等バイオマス発電・バイオマス液体燃料
電源 規模 (参考)2020年度 2021年度
バイオマス発電 (一般木材等) 10,000kW未満 24円+税 24円+税
一般木材等バイオマス発電(10,000kW以上)・バイオマス液体燃料(全規模)
2021年度の買取価格は入札により決定。上限価格は非公表。
まとめ
今回は21年度FIT買取価格を決定に関しての情報に関してお伝えしてきました。
一部は既に決定していた内容もありますが、今後も最新の情報を皆様にお届けしていきます。