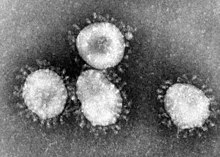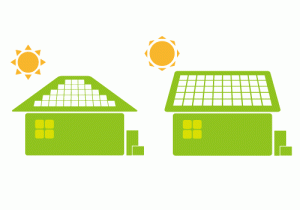省エネ推進を行うことで活用できる省エネ補助金や税制優遇があることは今までのブログでも度々紹介してきましたが、金融機関の融資について省エネや環境に配慮したことで加点される融資があることはご存知でしょうか?各金融機関によって制度は異なると思いますが日本政策投資銀行でもこのような融資は存在します。今回のブログは、このような省エネや環境に関する金融機関の取り組みについて、ご紹介していきたいと思います。
「環境格付」に基づく融資を実施!?
日本政策投資銀行は、3月3日、ポリプラスチックス(東京都港区)に対し「DBJ 環境格付」に基づく融資を実施したと発表しました。この指標は企業の環境経営度を評点化し、得点に応じて3段階の金利を適用する融資メニューとなります。(なお、ポリプラスチックスは、「環境への配慮に対する取り組みが先進的」という格付を取得しています。)
「海外拠点も含めESH監査実施」等が評価
今回の格付けでは以下の点が評価されています。
・海外グループ拠点も含めたESH(環境、安全・防災、健康)監査の実施やパフォーマンスデータの開示に加え、グループ全体のサプライチェーン管理においてCSR配慮を促進している点
・コントロールセンターにて製造工程を見える化し、プラントの稼働状況や電力使用量、水使用量等の常時モニタリングを通じて、製造の最適化・効率化やエネルギー使用量の削減を推進している点
・社内のCSR活動を統合すべく、CSR委員会やCSRグループを新たに設置し、中期経営計画やSDGsを踏まえ、全社的にビジネスと社会課題の解決を同期させたCSR計画の策定を進めている点
・ポリプラスチックスは、環境負荷低減樹脂の開発・製造を手掛ける。経営理念である「エンジニアリングプラスチックスの無限の可能性を追求し、才能豊かな魅力溢れる人材の創出と、Innovation による豊かな未来社会の形成に貢献する。」実現のため、「事業活動そのもので社会に貢献すること」「事業活動を通じて社会を良くする機会を提供する」のふたつの側面からCSRに取り組んでいる。
「DBJ環境格付」融資は、日本政策投資銀行が開発したスクリーニングシステム。環境経営への取り組みが優れた企業を評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定する「環境格付」の専門手法が導入されています。2004年から運営を開始。2014年度評価項目を大幅に見直し、「GRI(Global Reporting Initiative)」のガイドラインでも強化されたマテリアリティやKPIといった概念が盛り込まれています。
まとめ
金融機関における省エネに対する取り組みは、これ以外にも数多くの事例が存在します。省エネ推進に取り組まれている会社であれば、活用できる融資制度も多く存在していると思いますので是非参考にしていただければと思います。