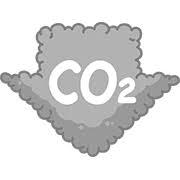環境省は7月13日、事業場や工場を対象に、エネルギー起源二酸化炭素排出抑制のための先進的で高効率な低炭素機器の導入を支援する「先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業」(ASSET事業)について、98件の採択事業者を発表しました。
採択された98件の内訳は、単独参加(事業場)37件、単独参加(工場)47件、グループ参加(事業場)6件、グループ参加(工場)8件となっています。今回のブログは、この「先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業」(ASSET事業)ついて、ご紹介していきたいと思います。
「CO2大幅削減設備」の補助事業、20年度は98件を採択 2次募集実施中?
環境省は7月13日、事業場や工場を対象に、エネルギー起源二酸化炭素排出抑制のための先進的で高効率な低炭素機器の導入を支援する「先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業」(ASSET事業)について、98件の採択事業者を発表しました。採択された98件の内訳は、単独参加(事業場)37件、単独参加(工場)47件、グループ参加(事業場)6件、グループ参加(工場)8件となっています。
採択案件に関する2021年度排出削減目標量の合計は45,945トン―CO2(事業場合計:11,180トン―CO2、工場合計:34,765トン―CO2)。ASSET事業対象L2―Tech認証製品の「設備・機器等」は22区分(対象45区分)となっています。
導入設備の法定耐用年数分の排出削減予測量の合計は、510,788トン-CO2(2021年度排出削減目標量が法定耐用年数の期間、毎年度削減実績として続いた場合)となります。
2次募集は8月20日正午まで
なお、同事業の2次公募は7月13日より開始されており、締め切りは8月20日正午まで。公募説明会は実施せず、説明資料はウェブサイトに公開されています。
同事業は、高効率な低炭素機器(L2-Tech認証製品等)の導入によりCO2排出削減目標を掲げ、その目標達成を約し、事業の参加者全体において排出枠の調整を行い、事業全体として確実な排出削減を目的とし、それら低炭素機器の導入を支援するものとなります。補助率は、条件により1/2~1/3、実施事業者あたりの補助金の上限は1億円。
同事業は2012年度より、業務部門・産業部門における温室効果ガス排出量の大幅削減のため、実施されてきました。2020年度は5月8日から6月16日まで公募が行われています。
まとめ
CO2の削減は日本全体で掲げている至上命題であるともいえます。今後も間違いなく注目されていく分野の1つであると言えます。是非皆さまもCO2削減について考えてみては如何でしょうか?