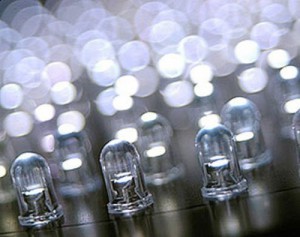昨今のコロナウイルスの影響で売上減少や営業時間の制限などの影響が出ている企業も多いのではないかと思いますが、行政は変わらずに期日通りの遂行をしていくため、それに追いついていかなければならないことも多くあります。書類の提出期限、税金の納税期限、各種申請の申請期限など・・・。様々なものがあらかじめ決められた期日として存在しています。しかし、今回、このようなコロナウイルスの状況を鑑みて、「省エネ法」関係書類の提出等期限を延長されることが決定されました。様々な理由で通常業務を稼働できない方にとっては朗報なのではないでしょうか?
省エネ法関係書類の提出等期限を延長 新型コロナ感染拡大に対応!?
経済産業省は4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、省エネ法に係る2020年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じると発表しました。
工場等・荷主に係る定期報告書など、省エネ法の関係書類について、例年では4月末日または5月末日までに提出が求められている書類の提出期限は7月末日までに延長し、6月末日または7月末日までに提出が求められている書類の提出期限は9月末日までに延長することとしています。
又、新型コロナウイルス感染症対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。これに伴い、多くの事業者において、省エネ法に基づく定期報告書の作成業務などを例年どおりに進めることが困難になることが想定されています。
こうした状況を踏まえ、省エネ法関係書類の作成に十分な時間を確保できるよう、省エネ法に基づく省令を改正し、2020年度に限り、関係書類の提出期限を延長することになりました。
また、省エネ法に基づき特定事業者等に求められているエネルギー管理企画推進者とエネルギー管理員の選任については、2019年12月1日から2020年5月末日までの間に選任すべき事由が生じた場合に限り、選任期間を半年間延長する。具体的には「選任すべき事由が生じた日から6月以内」から「選任すべき事由が生じた日から1年以内」へと延長する。今回の感染拡大により、2020年度上期のエネルギー管理講習の開催のめどが立っていないことを受けたものです。
今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、対応をさらに変更する可能性もあるります。具体的な工場等に係る定期報告書等と、荷主に係る定期報告書等の2020年度における提出期限は以下の通りとなります。
工場等に係る定期報告書等の提出
| 義務の内容 | 例年の提出期限 | 2020年度の提出期限 |
| エネルギー使用状況届出書の提出 | 5月末日 | 7月末日 |
| エネルギー管理統括者の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
| エネルギー管理企画推進者の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
| エネルギー管理者の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
| エネルギー管理員の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
| 中長期計画書の提出 | 7月末日 | 9月末日 |
| 定期報告書の提出 | 7月末日 | 9月末日 |
荷主に係る定期報告書等の提出
| 義務の内容 | 例年の提出期限 | 2020年度の提出期限 |
| 輸送量届出書の提出 | 4月末日 | 7月末日 |
| 中長期計画書の提出 | 6月末日 | 9月末日 |
| 定期報告書の提出 | 6月末日 | 9月末日 |
まとめ
全国的な活動自粛の動きも相まって、行政関係の書類が不十分になってしまうことはあり得るかと思います。改めて皆様が必要な書類の提出期限をご確認いただきたいもので