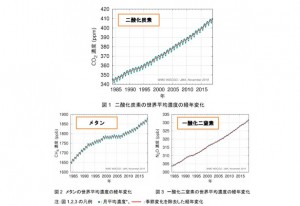皆さんは補助金申請が一部電子申請システムを導入することはご存知でしょうか?
経済産業省は2020年より、補助金申請に、インターネットを利用して申請・届出をする電子申請システム「Jグランツ」を導入します。
これにより、事業者はいつでも・どこでも申請が可能となり、書面で行う申請に比べて手間やコストを削減することができるようになります。
今回は補助金申請の電子申請システム化に伴う情報をご紹介していきます。
経産省、20年から補助金申請に電子申請システム導入 ID登録を呼びかけ
経済産業省の補助金では、2019年度補正、2020年度当初予算で27補助金が対象となる。Jグランツ上でリアルタイムに申請状況や処理状況が把握できるため、手続を迅速に行うことができる。また、他省庁や自治体の補助金も含めて随時拡大をしていく予定です。
また、Jグランツにはと自治体の補助事業が掲載され、ワンストップで、補助金情報を収集することができる。各補助金の公募準備ができ次第、「補助金一覧」に補助金名が掲載されます。
法人共通認証基盤(GビズID)の早期取得について
Jグランツを利用するには、事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム「GビズID」のうち「gBizプライム」を取得する必要がある。共通のアカウントを利用することにより、社名や住所など、中小事業者等も含む法人の基本情報については、何度も入力する必要がなくなる(ワンスオンリー)。GビズIDの取得には、2~3週間程度の審査期間が必要となるため、公募開始前からのGビズIDを取得するよう呼びかけています。なお、GビズIDは無料で取得できます。
公募から事業完了後の手続をオンライン化
世界的にも補助金申請を含めた行政のデジタル化が進展していることも踏まえ、経済産業省は、公募から事業完了後の手続までをオンラインで完結可能な汎用的な補助金申請システム「Jグランツ」を開発し、リリースした。ワンストップ・ワンスオンリーによる補助金申請を実現し、事業者の利便性向上を目指します。
具体的な手間やコストの削減として、移動時間や交通費・郵送費などのコストが削減できる、過去に申請した情報の入力や、書類の押印が不要になるなどのメリットをあげられます。
まとめ
今回は補助金申請に電子申請システム導入化に関してご紹介しました。
従来の多くの補助金申請は、紙での手続が主流であり、大量の紙での申請や郵送などの手続が煩雑であり、補助金を利用したい事業者が気軽に申請できる環境ではありませんでしたが、今回の電子化によってどれほど効率が上がるのか、今からとても楽しみですね。