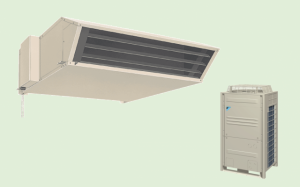前回のブログでは企業の災害時の対策(広義の考え方では、BCP対策)について紹介をさせていただきました。今回の台風被害でも言えることですが、災害時の対策はなにかあってからでは遅く、事前に対策を行っていくことが必要になります。是非皆さまも非常時の対策としてご参考にしていただければと思います。
BCP対策の種類
BCPの対象となる非常事態とは、【自然災害:巨大地震・水害・竜巻など】【外的要因:仕入れ先の倒産・サイバー攻撃など】、【内的要因:バイトテロ、自社の不祥事により役員の退職など】に分類されます。そのため、マニュアルもそれぞれの非常事態用に細かく分類されています。
自然災害のBCP対策マニュアル
自然災害の場合、人名救助の方法・避難方法・安否確認方法・被害状況の確認・停止した事業を代替設備で復旧させる方法を記載する必要があります。停電に備え、紙媒体で管理することもあるでしょう。自然災害に対する対策もBCP対策の1つといえます。
外的要因のBCP対策マニュアル
仕入先が倒産した場合、仕入先の二重化・変更先リストを策定する必要があります。
サイバー攻撃を受けた場合、社員・顧客・株主などの利害関係者に説明責任が問われます。その通知内容/方法を決めておく必要があります。このような外的要因の対策もBCP対策の1つといえます。
内的要因のBCP対策マニュアル
バイトテロの場合、発覚すればクレームが多数寄せられ、窓口の増加やクレーム用スクリプトの準備などの対応が必要です。バイトテロとは、飲食店などでアルバイトとして雇用されている店員が、店の商品・場所などを使って悪ふざけを行うさまをSNSに投稿して炎上し、企業に教育面・衛生面などで被害がでることを指します。このような内的要因への対策もBCP対策の1つといえます。
これらのように、さまざまな要因によって事業継続が難しくなるので、考えられるリスクを想定しマニュアルの策定や対策をしていくことが重要になります。
防災対策の違い
BCPは自然災害含め、すべての非常時が該当します。上記で説明した通り、自然災害要因以外にも外的要因・内的要因があります。突然の停電、原子力事故、テロ、インフルエンザ感染、リコール、食中毒と様々な脅威があります。それに対して防災対策は、地震対策や洪水対策などの自然災害のみが対象となります。
又、BCPは現物を守ることではなく、事業の継続性を守ります。そのため、自社だけにとどまらず取引先の企業と、共同で対策を練り経営資産を確保することもあります。共同化の例として、地域金融機関において共同バックアップセンターを持つケースが多いとされます。高価な金融システムの運用を共同で行うことで、コスト削減にも繋がります。防災対策は、自然災害から現物資産を守るため自社のみの対象になります。
まとめ
如何でしょうか?BCP対策についてご理解いただけたでしょうか?それでは次回のブログではこのBCP対策において、どのような具体的な対策ができるかをご紹介していきたいと思います。