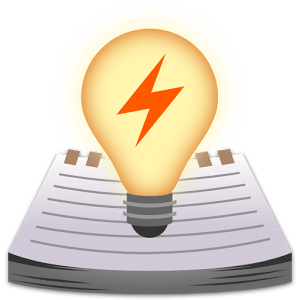前回の記事をご覧になっていただいた方は太陽光発電メーカーの海外と国内の違いを見ていただけたのではないかと思います。
それではなぜ海外では中国メーカーがシェアを大幅に占める中、国内では日本メーカーに需要が8割も占めているのでしょうか?
品質に対する需要は何となく皆さんもあるのではないかとご想像されていると思います。
今回は日本メーカーの需要が高い国内の太陽光市場に関しての情報をご紹介したいと思います。
なぜ国内では日本メーカーが人気なのか!?
日本メーカーの市場が国内で減らない理由はまずは品質です。
10年~20年と長期間稼働させなければならない太陽光発電システムは故障がしにくいというのも重要なポイントなのです。
また、定期的なメンテナンスや不具合時のアフターサービスも不可欠であり、その点も日本メーカーが最も身近に感じられるために、安心感を与えてくれるのだと思います。
海外メーカーと比べてどのようなメリットが考えられるか?
海外の太陽光発電メーカーでは中国のサンテックパワーが2013年に再生支援を受けており、ドイツの大手太陽光発電Qセルズは2017年に破綻しました。
国内メーカー全体としては縮小傾向にあるといわれていますが、日本の市場は国内メーカーを優遇ししている点など、現在海外の大手メーカーのような経営不振に陥っている大手企業はいません。
長期的に太陽光発電のサポートやメンテナンスを依頼しようと考えたときに、言語の壁に当たったり、上記のように急な理由で対応ができなくなるということもリスクとしては考えておく必要があるでしょう。
つまり、海外シェアという点では現状中国に勝るメーカーは出ていませんが、国内シェアでは上位が国内メーカーを占めており、引き続きこのシェア率は大きくは変動しないと考えられます。
まとめ
前回は海外メーカーと日本メーカーのシェア率をそれぞれご紹介しましたが、今回の内容では日本メーカーが国内で選ばれている理由も少しご理解いただけたのではないでしょうか?
次回も引き続き海外メーカーと日本メーカーの比較に関してご紹介していきます。
『 太陽光発電日本メーカーの国内シェア率について 』
投稿日: 2019年5月31日 作成者: admin
皆さんは国内の太陽光パネルメーカー以外に海外の太陽光パネルメーカーをどのくらいご存知ですか?
太陽光発電メーカーの海外シェアはあまり国内では目立っていませんが、実は太陽電池やモジュールのシェアもアメリカやドイツのメーカーが上位を占めているのです。
今回は海外の太陽光発電パネルメーカーに関しての情報をご紹介したいと思います。
太陽光発電メーカーに関して海外、もしくは日本どちらか良いか悩まれている方は参考にしてみてください。
海外の太陽光メーカーについて
海外の太陽光発電メーカーのトップシェアは中国企業です。理由は安価であることもそうですが、品質も世界で認められているレベルであるということも分かります。
過去にはシャープがトップ10に入っていたこともありますが、直近5年では日本メーカー中国メーカーなどに世界のシェア率は劣っていることが分かります。
海外の太陽光発電メーカーシェアランキング2019
1位 Jincosolar(中国)
2位 Trinasolar(中国)
3位 Canadiansolar(製造が中国、本社はカナダ)
4位 JAsolar(中国)
5位 HanWhasolar(韓国のハンファグループが運営しているが中国とドイツメーカーを買収済み)
6位 GCL-SI(中国)
日本の太陽光発電メーカーについて
日本でのトップシェアはパナソニックです。また、日本メーカーで国内の太陽光発電のシェア率は合計84パーセントになります。
海外のでは中国メーカーが市場を占める傾向がみられる中、国内メーカーに品質や信頼感をよせている方々も多くいることが分かります。
日本の太陽光発電メーカーシェアランキング2019
1位 パナソニック(20%)
2位 京セラ(20%)
3位 シャープ(18%)
4位 東芝(10%)
5位 三菱電機(8%)
6位 ソーラーフロンティア(8%)
まとめ
海外メーカーが良いのか?日本メーカーが良いのか?は各々の見解があるかとは思いますが、
上記の結果を見ると、安価な中国の製品にはどの国も対抗できていないことが分かります。
次回は日本メーカーが国内でシェア率が高い理由に関してご紹介していきます。
『 太陽光発電パネルメーカーランキング 』
投稿日: 2019年5月31日 作成者: admin
皆さんはソーラーシェアリングという事業をご存知でしょうか?
ソーラーシェアリングとは農林水産省では営農型発電設備と呼んでおり、農業を継続しながら発電を行う事が出来ます。
今回はソーラーシェアリング事業についてご紹介したいと思います。
ソーラーシェアリング
農林水産省では営農型発電設備と呼んでおり、農業を継続しながら発電を行う事が出来る事業をいいます。また、ソーラーシェアリングは他の太陽光発電設備とは異なり、農作物の栽培と一緒に売電事業を行うことで、営農の継続をサポートすることが主の目的となります。
ソーラーシェアリングのメリット
ソーラーシェアリングを設置することで、得られるメリットは3点あります。
・農作物の栽培と同時に効率よく発電ができる
・余剰分の太陽光をソーラーシェアリングに有効利用できる
・ソーラーシェアリングに適した作物はより品質が上がる
農業を続けることをメインとした発電事業なので、栽培する作物の育成を妨げないことが大前提ですが、農作物の栽培と同時に効率よく発電できるということがメリットであるといえます。特に芋類、穀物類、葉物類、果樹の一部やソーラーシェアリングで収穫量が増えたり、元類は葉っぱが柔らかくなったという事例もあるようです。
また、太陽光パネルによって太陽の光がさえぎられて、作物の育成の妨げになると考える人もいるかと思いますが、ソーラーシェアリングの考えはCHO研究所所長の長島彬氏の研究によるもので、植物に与えすぎても無駄や害になってしまう太陽光を発電に活かすということが元の概念となっています。
ソーラーシェアリングを実施するための農地区分条件
農業を行うための土地のことを農地と言いますが、農地は幾つかの種類に分けられています。
第3種農地・第2種農地
これらの二つの地域は市街地にある農地、今後市街地になる可能性がある地域の農地など、生産性の低い農地を指し、他の用途で土地を利用するための「転用」許可が受けられるため、一般的な太陽光発電設備にも使われてきました。
第1種農地、甲種農地
これらの農地は農業を行うにあたって好条件であることなどから、農業の継続が強く推奨されているため、「転用」による太陽光発電の設置等は原則的に認められていません。また、これらの農地の区分とは別に市町村が指定する「農用地区域」という土地があり、この指定を受けた農地も農業以外の用途に使うことが原則として認められていません。
ただし、甲種・第1種農地や農用地区域の農地でも、ソーラーシェアリングという形であれば太陽光発電が可能になります。
ただし、ソーラーシェアリングの設置許可は、農地の一時転用許可という形で行われるため、許可期間の3年間が過ぎると新たに許可を取り直す必要がある点には、注意が必要です。
ソーラーシェアリングには農地で太陽光発電事業ができること、作物の生育にプラスになる部分があると同時に、農業をしっかりと続けられなければ事業をやめなければならないというリスクがあることも理解しておく必要があるでしょう。
まとめ
ソーラーシェアリングの最大のメリットは本業にとって良い効果が得られるという点にあり、今までこの手の話を聞かれたことがない農家さんが周りにいらっしゃれば、皆さんの口から情報としても伝えてあげても良いかもしれません。
『 ソーラーシェアリングとは!? 』
投稿日: 2019年5月31日 作成者: admin
皆さんは太陽光発電などの再生可能エネルギー電源を対象とする出力制御、今後その対象となる発電設備の規模が広がる可能性があることをご存知でしょうか?
経済産業省は九州電力管内において出力制御が急増していることなどを受け、対象となる太陽光発電の規模を500kW未満にも拡大する方針を示しています。
今回は太陽光発電システムの太陽光発電の出力制御についてご紹介したいと思います。
太陽光発電などの再生可能エネルギー電源を対象とする出力制御
経済産業省は九州電力管内において出力制御が急増していることを受け、公平性の観点から、対象となる太陽光発電の規模を500kW未満にも拡大する方針を示しています。
これまでの出力制御は、2015年1月25日以前にFIT定を行った設備を対象とする、いわゆる旧ルールが適用されている500kW以下の太陽光発電については出力制御の対象外とされてきました。
太陽光発電の導入が急速に広がった九州電力管内においては、2018年度に26回の出力制御を実施するなど、制御実施回数が急増しており、今後さらに出力制御の回数が増加する見通しです。
また、FIT認定案件の中でも件数の多い、旧ルール適用となる低圧の太陽光発電案件が制御対象から外れるというのは、事業者間の公平性に欠けるという指摘がでたことから、経済産業省では今後、旧ルール適用下にある500kW未満かつ10kW未満を除く案件についても、出力制御の対象とする方針を示しています。
まとめ
今回の話の対象となる案件が増えれば、1案件当たりの出力制御量を減らせるメリットも期待できます。
今後夏ごろまでに詳しい詳細も決まっていくとのことなので、今後も追っていきたいと思います。
『 太陽光発電の出力制御 』
投稿日: 2019年5月31日 作成者: admin
皆さんは太陽光発電設備を共同購入するという話を聞いたことがありますか?
神奈川県で住宅太陽光発電システムを複数のユーザーと共同購入することができる新しいサービスが始まりました。
今回は太陽光発電システムの共同購入という話についてご紹介したいと思います。
かながわスマートエネルギー計画
神奈川県では再生可能エネルギー等の導入を加速化し、エネルギーの地産地消を進める「かながわスマートエネルギー計画」を掲げ、太陽光発電の普及促進に取り組んでいます。
住宅用太陽光発電の共同購入事業
住宅用太陽光発電の共同購入事業とは、事前に購入希望者の参加登録、ならびに販売施工事業者の入札参加意向を募り、具体的なスケールメリットを把握したうえで入札によって価格を競い合うというものです。
共同購入に参加する消費者の登録受付は無料で、2019年5月17日より募集を開始し、登録をする時点では購入の義務は生じません。
同年6月20日に登録期間を終了し、その後入札により販売施工事業者を決定していく予定で、個別の見積もり提供を行います。購入希望者は同年8月8日までに購入を判断し施工が始まり、購入・施工は2020年3月に終了する予定です。
住宅用太陽光発電共同購入のメリットは、多くの人が参加することで共同購入が可能となり、販売施工事業者から神奈川県民に向けた特別な割引価格を得ることができるところにあります。
消費者へは市場価格の10~20%割安な価格での提供を目指しており、事前見積書で製品・価格、初期費用の回収年数を分かりやすく説明、納得したうえで購入の判断していただくという流れです。
さらに、太陽光発電の専門家が販売施工事業者を入札で選ぶことから、購入者は製品・販売会社・施工品質の比較検討などをする必要もないこともあります。
まとめ
太陽光発電システムの導入に関しては、各都道府県別で様々な施策を実施しています。導入を検討されている方やきっかけが今までなく、これから考えていきたいという方は自分がお住まいの地域の施策も一度検索してみると良いと思います。
『 太陽光を共同購入 』
投稿日: 2019年5月31日 作成者: admin
今回の省エネ補助金活用事例は、介護施設(特別養護老人ホーム)のLED・空調・断熱リフォームの施工事例です。エネルギーコスト削減について、医療機関や介護施設からのお問い合わせやご要望も多くなってきています。

施工提案内容
特別養護老人ホームAのエネルギーコスト削減工事は以下の内容になります。
蛍光灯型LEDへの照明更新工事 約200本
空調機の更新工事 5台
断熱リフォーム工事
当初の施工計画では設備単位の補助金の活用が可能でしたが、断熱リフォーム工事を加えることで事業所単位の活用が可能となりました。補助金は出ないものと担当者の方は思っていたので、それが一気に事業所単位の活用まで可能となり、施工内容や費用面に大変ご満足を頂くことができました。
施工完了ならびにエネルギーコスト削減効果
入所型の介護施設は、特に夏と冬は空調は24時間稼働となりますし、照明も長時間点灯させることになります。介護施設の収益環境から、エネルギーコスト削減は大きな課題となります。更新をした当年から成果を見ることができ、補助金によるコスト削減とともに、エネルギーコスト削減効果にもご満足を頂くことができました。
まとめ
現在はエネルギーコスト削減に関する補助金も多岐に渡っています。それについての専門家の方も多く、1つの事実に対して複数の見解が生まれることも少なくありません。しかし、今回の記事で複数回記載をしましたが、見解の相違はまだ良いと思いますが、誤った内容が伝達されそれを基に意思決定がされてしまうことは避けなければいけません。
誤った情報を伝達してしまった人も、多くの場合は意図してそれを行ったわけではありません。一生懸命営業活動をしようとした結果によるものですが、当社はこの分野に長く携わっている専門家として、毎年変化する補助金等の情報を正確に理解し、その活用方法の提案等も含め正しい情報の発信に努め、お客様のエネルギーコスト削減に引き続き寄与していきたいと考えています。
『 省エネ補助金活用事例16-2 ~介護施設(特別養護老人ホーム)の補助金活用事例~ 』
投稿日: 2019年5月29日 作成者: admin
今回の省エネ補助金活用事例は、介護施設(特別養護老人ホーム)のLED・空調・断熱リフォームの施工事例です。エネルギーコスト削減について、医療機関や介護施設からのお問い合わせやご要望も多くなってきています。

施工対象施設情報
今回施工対象となりました介護施設は下記の内容になります。
会社 特別養護老人ホームA とします
運営母体 社会福祉法人B
所在地 愛知県内
定員 90名
施工実施前の状況
特別養護老人ホームAは定員90名の中型の介護施設で、地元密着、地域に根差した運営を行っている介護施設です。
現在、多くの介護施設が建設から10年以上が経過し、様々な設備が更新を考えなければいけない時期になっていること、新築の時に建設をした建設会社も、すべての建設会社が設備更新を得意としているとは限らないこと、入所者が少ないというわけではないが、経営環境として大幅な利益が確保できる業態でもないこと、などの理由から、近年は介護関連施設からのエネルギーコスト削減についての相談が増えています。
エネルギーコスト削減を行う建物という観点から言うと、代表的なものの1つに製造業の工場があげられます。弊社も製造業の工場の施工を数多く取り組ませて頂いてきましたが、製造業工場と介護施設の最も大きな違いは、その企業や施設の担当者の方の電気系統や関連分野に関する経験や知識量に違いがあることです。製造業工場の現場で電気関連に携わっている方は一般的に専門知識や経験値が豊富で、この分野の経験がない人がこのようは方々に何かを提案しようと思っても、その経験や知識量が追いつかないため有効な提案を行うことが難しくなることが多くあります。
しかし、介護関連施設の設備を担当している方は、製造業の工場の担当者の方のほど経験や知識量が豊富ではない方も多く、そのため多くのエネルギー分野に新規参入をしてきた企業の営業活動を受けることにもなります。新規参入企業は電気関連の経験や知識量が乏しいため、工場に営業活動を行っても歯が立たず、介護施設であれば多少知識がなくても営業活動を行うことができる、と考える人も少なからず存在しています。
よって介護施設の担当者は、経験や知識が乏しい担当者からの提案を受ける機会もそれなりに多く、そのためそのような担当者から極端に言えば誤った情報がもたらされていて、それを本当のことと信じてしまっていることもあります。この特別養護老人ホームAの担当者がまさしくその状態で、照明のLEDへの更新や空調工事を行いたいと考えていたのですが、以前提案をした業者から補助金は使えないと言われていたため、補助金が使えないものだと思い込んでいました。
実際には十分に補助金が活用できる施工計画であり、さらにその後に計画されていた断熱リフォームなども加えれば、設備単位ではなく事業所単位の補助金も活用できる内容でした。弊社の提案により正しい認識を持って頂くことができ、非常に喜んで頂けた事例となります。
まとめ
エネルギーコスト削減は国としても重点分野に位置づけられており、そのために各省庁がそれに関わる補助金も出しています。国がこの産業を後押ししますので、多くの企業にとってもビジネスチャンスであることには間違いなく、経験や知識がない新規参入企業が数多く存在することも間違いのないことです。
もちろんどの企業も一生懸命営業活動を行いますので、多少の知識のなさや経験の乏しさも営業力やトーク力でカバーをしようとします。これそのものは弊社も含めお互い様の面もあるので強く否定をするものではありませんが、しかしやはり誤った情報が伝達されていてそれを基に意思決定をしてしまっては、せっかく大幅な施工費のコストダウンができるにもかかわらずその機会をみすみす失ってしまいます。弊社は補助金等の正確な情報を常に発信することを心掛け、必要とされるエネルギーコスト削減を必要最低限のコストで実現することに引き続き力を入れていきます。
『 省エネ補助金活用事例16-1 ~介護施設(特別養護老人ホーム)の補助金活用事例~ 』
投稿日: 2019年5月29日 作成者: admin
今回のブログも前回から引き続き、国土交通大臣から交付されている「住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業」についてご紹介を行っています。前回は主にサステナブル建築物等先導事業についてご紹介を行っていきましたが、今回は中小規模建築物の改修工事で活用できる既存建築物省エネ化推進事業について紹介していきたいと思います。会社事務所や工場で建屋・設備担当をされている皆さまは是非参考していただければと思います。

既存建築物省エネ化推進事業とは!?
この補助金は、民間等が行う省エネ改修工事に対して、改修後の省エネ性能を表示することを要件に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する内容となっています。これにより社会全体の建築物ストックの省エネ改修等の促進を行うことを目的としています。
応募要件としては、
・躯体(壁、天井等)の省エネ改修を伴うものであること
・改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれること
・改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと
・省エネ性能を表示すること
・原則として採択年度内に完了すること
・事例集等への情報提供に協力すること
となっています。
その補助対象としては、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、エネルギー測定等、省エネ性能の表示 となっており、補助率は対象工事の1/3、限度額は5,000万円となっております。
具体的な工事内容の例としては、躯体改修工事でいえば外壁・屋根に関する断熱・遮熱対策、遮熱フィルムの活用、設備改修工事でいえば空調設備、照明設備、給湯設備、換気設備、昇降機などの省エネ性能向上などが挙げられます。
又、採択率に関してみると平成29年度は応募件数に対して採択率は90%を超えている現状でしたが平成30年度は40%弱となっております。
しかし、半分が採択されるという考え方で見るのであれば悪くはない数字なのではないでしょうか?
補助金の分野は単なる改修工事を行うだけでは当然駄目で、対象条件に合うように工事内容を組み、必要書類の提出を含めて行っていく必要があります。
採択率が悪いから省エネ補助金は活用出来ないといった声を聞くこともありますが、きちんと要件に当てはまった内容で実施できているかどうかはポイントになってくると思います。
まとめ
省エネ補助金は種類や内容が複雑なだけでなく採択を取るためには知識とノウハウが必要な分野となってきます。どのように申請を出すかによって採択されるかどうかが大きく変わるのです。このような分野はご自身で全てを学ぶよりも専門家を味方につけた方が効率的だといえます。(工事業者であっても省エネ補助金に詳しくない業者はたくさん存在しますので注意が必要です。)是非正し知識を身につけて皆さまに有利な建屋改修・設備改修を
『 令和で活用できる省エネ補助金!?③ 』
投稿日: 2019年5月16日 作成者: admin
今回私どものブログでは国土交通大臣から交付されている「住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業」についてご紹介を行っています。前回のブログでお伝えしたサステナブル建築物等先導事業、地域型住宅グリーン化事業、既存建築物省エネ化推進事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業、省エネ街区形成事業とはどのような内容なのでしょうか?
今回はサステナブル建築物等先導事業と既存建築物省エネ化推進事業について概要に触れていきたいと思います。

サステナブル建築物等先導事業とは!?
サステナブル建築物等先導事業のなかにも補助金の種類はたくさんあるのですが、今回は省CO2先導型について紹介していきたいと思います。
これは先導性の高い住宅、建築物の省エネ・省CO2プロジェクトについて民間等から提案を募り支援を行っていく補助になります。事業の成果を広く公表することで取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを目的としたものになります。新築については一般住宅、中小規模建築物のいずれも適用対象なのですが、改修工事については中小規模建築物が適用対象外となっております。
事業の要件としては、
・それぞれの部門で定められた省エネルギー性能を満たし、省エネルギー性能の表示を行うもの
・運用後のエネルギー使用量の計測、CO2削減効果実証に関する計画書を提出するもの
・平成31年度に事業着手するもの
・住宅、建築物プロジェクト総体として省CO2を実現し、先導性に優れているプロジェクトであること
となっています。
この基準に当てはまる省エネ・省CO2プロジェクトを民間から公募して採択を行っていくことになります。
サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)について
サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)は、一般部門(非住宅)、中小規模建築物部門、一般部門(共同、戸建住宅)、LCCM部門(戸建住宅)がありますが、それぞれ省CO2に優れたプロジェクトで且つ有識者員会で評価されたもの(若しくわ要件を満たすもの)であることが条件とされています。
補助金額は設計費・建設工事費の1/2までとされており、補助上限は原則5億円とされています。
まとめ
この補助金は中小規模建築物の場合は改修工事での適用ができないため、会社で設備担当をされている皆さまにとっては、主には新築工事の際に活用できる補助金として捉えていただくといいかと思います。次回のブログでは改修工事の際に活用できる補助金を紹介していきたいと思いますので是非参考にしていただければと思います
『 令和で活用できる省エネ補助金!?② 』
投稿日: 2019年5月16日 作成者: admin
今までのブログでも省エネ補助金は数多く紹介させていただきましたが、今年度も数多くの省エネ補助金は各省庁から交付されています。メジャーなものから新しいものまで数多くの種類があるため、専門的に関わっている担当者でなければ全容を把握することは難しいのではないでしょうか?
今回私どものブログで紹介させていただく内容はそんな省エネ補助金のなかでも「住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業」に関わるものを全3週に渡ってご紹介したいと思います。令和元年の内容が先日発表された最新事情をお伝えできればと思います。

住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業って!?
住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業は国土交通省が交付している補助金になります。現在全国各地で説明会を実施しており、改定された内容も踏まえて今後活用していきたい補助金の1つとなっています。
省エネに関する政策動向?
1990年比で見た時に産業部門、運輸部門はエネルギー消費量が微増、若しくわ、減少している状況にあります。しかし、業務部門、家庭部門については90年比で20%近く増加しており、全エネルギー消費量の約3割を占めるほどになっています。このような背景から引き続き建築物における省エネルギー対策の強化は急務であると言われています。
又、2015年のCOP21においてパリ協定を採択し、日本は2030年に2013年度比で26%のCO2削減を約束しています。この実現をするために業務部門、家庭部門においては2013年度比で約40%のCO2削減を行っていく計画を打ち出しています。
新築住宅、新築建築部の省エネ性能の向上、既存建築物の省エネ推進を行うことは、引き続き国として取り組まなければならない状況であるといえます。
どのような補助金があるの?
住宅・建築物に関する主な省エネ推進施策として融資や税制優遇や補助金があるのですが、今回の住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業で適用される補助金としては、サステナブル建築物等先導事業、地域型住宅グリーン化事業、既存建築物省エネ化推進事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業、省エネ街区形成事業といったものがあります。今回はこのなかでもサステナブル建築物等先導事業と既存建築物省エネ化推進事業について触れていきたいと思います。ともに新築工事、改修工事のいずれでも活用できる内容ですので、覚えておいて損はない内容となっております。
まとめ
省エネ補助金は数が多く毎年制度内容も変わっているため内容を把握することがとても難しい内容となっています。しかし、これだけ国策として打ち出している事業であれば国の支援を活用しない手はないといえます。皆さまの建物を新築、改修工事される際にはしっかりと活用したいものですね。
『 令和で活用できる省エネ補助金!? 』
投稿日: 2019年5月16日 作成者: admin
今回の省エネ補助金活用事例は、ある食品工場のLEDとキュービクルの更新工事の事例です。当初はお客様自身も補助金活用を考えていた案件ではなく、弊社のエネルギーコスト削減に対する考え方をよく反映させて頂いた事例となります。

施工提案内容
株式会社Aのエネルギーコスト削減工事は以下の内容になります。
水銀灯のLEDへの更新工事 8基
キュービクルの更新行為 1基
活用した補助金は設備単位の補助金を活用しました。それぞれ単体では補助対象ではありませんでしたが、2つをまとめることにより補助対象とすることができました。
施工完了ならびにエネルギーコスト削減効果
今までも記載をしたことがありますが、照明や電気系統のエネルギーコスト削減工事は削減効果のシミュレーションと結果に差がほとんど生まれないことが特徴です。工場の電気系統は決して簡単な工事ではないことが多いですが、当社の経験を活かして確実に工事を行い、想定していたエネルギーコスト削減効果を得ることができています。
まとめ
エネルギーコスト削減の取り組みは中長期の取り組みとなります。1つの内容では補助対象にならない内容でも、2つ3つの内容をまとめると補助対象とできるものも数多くあります。しかし、翌年さらにその翌年と計画していた内容を、1年2年前倒しすることは通常はできません。まとめて行おうとすれば計画を後ろに送っていくことになります。
確かに毎年実施を予定していた計画からは遅れてしまうかもしれませんが、それによって補助金が活用できるのであれば、それに余りあるだけの施工コストの削減を行うことができます。弊社は今目の前にやりたいものだけではなく将来の計画も伺い、同時実施であれば補助金活用ができるのであれば、「計画の積極的な後ろ倒し」もお勧め
『 省エネ補助金活用事例15-2 ~食品工場の補助金活用事例~ 』
投稿日: 2019年4月26日 作成者: admin
今回の省エネ補助金活用事例は、ある食品工場のLEDとキュービクルの更新工事の事例です。当初はお客様自身も補助金活用を考えていた案件ではなく、弊社のエネルギーコスト削減に対する考え方をよく反映させて頂いた事例となります。
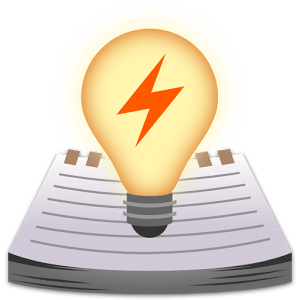
施工対象企業情報
今回施工対象となりました食品工場は下記の内容になります。
会社 株式会社A とします
業種 コンビニ弁当ならびに惣菜等の食品製造業
所在地 三重県内
施工実施前の状況
株式会社Aは食品製造業で、主にコンビニ弁当や惣菜等の製造を行っています。長時間稼働していることが多い業種でエネルギー使用量も多く、以前に空調機の更新は行われていましたが、今回は水銀灯をLEDに交換することを検討されていました。
担当者様は省エネ補助金のこともよく勉強していて、どのような補助金があるかもご存知でした。その上で今回の照明の更新工事は規模的にも内容的にも補助金対象外と考えていて、通常の見積もりを行いその後に通常発注での電気工事を行う予定をしていました。
そのような中で弊社も担当者様と面談の機会を頂くことができたのですが、お話を伺うと照明の更新の後に、さらにその翌年を考えているということでしたが、キュービクルの更新を考えているというお話が出ました。
エネルギーコスト削減は毎年の取り組みをしなければならず、今年は水銀灯のLED化を行い、来年はキュービクルの更新を考えているということでしたが、弊社からの提案は今年の予定をしていた水銀灯のLED化を見送り、来年にキュービクルの更新と同時に行ってはどうか?という提案をさせて頂きました。
その理由としては1点で、水銀灯のLED化とキュービクルを同時に行うと補助金の対象とすることができるからです。2つの工事を別々に行うと当然通常の費用がかかりますが、2つを同時に行うと1/3以上の補助が付く可能性があります。担当者様にもこの点をよくご理解を頂き、その翌年に補助金を活用して水銀灯のLED化とキュービクルの更新工事を行わせて頂きました。
まとめ
製造業を中心に、エネルギーの大口需要家は毎年エネルギー消費量の削減を求められています。そこに一定の予算がつけられ、毎年何かの取り組みをしなければいけない現状にあります。しかし、エネルギー消費量削減というものは一過性のものではなく中長期のものであり、今年実施することも来年実施することも中長期で見るとあまり変わらないということもあります。
もちろん事業年度ごとにエネルギーコスト削減の取り組みをコンスタントに行っていくことは大切ですが、2年分の取り組みを1度に行うことにより1/3以上の補助金が出るのであれば、弊社は検討に値する提案ではないかと考えています。利益が出ている今年のうちにやりたい、来年はどうなるか分からないということもよく分かりますが、先を見据えた収益の計画が少しでも見通せるのであれば、2年~3年分のエネルギーコスト削減の取り組みを1度にまとめて補助金を活用する方法も有効と考えます。
『 省エネ補助金活用事例15-1 ~食品工場の補助金活用事例~ 』
投稿日: 2019年4月26日 作成者: admin
皆さまがお使いになられている空調設備(エアコン)について、調子が悪くなってきたら修理をすることは当然のことかと思います。しかし、調子が悪くなってきたから修理を繰り返していたのでは非常に非効率である上、稼働効率の悪い空調設備をいつまでも使い続けていることになります。空調設備は定期的に更新工事をしていくことで稼働効率を保ったまま稼働することができるようになります。(又、その方が無駄な修理コストも掛からなくなります。)
今回のブログはそのような空調設備の更新についてご紹介していきたいと思います。

空調の更新ってなに?
基本的な話になると思いますが、そもそも空調の更新工事がどういったものかご紹介したいと思います。空調機器の更新工事とは、単なる取り替えではなく、将来を見据えて新しい価値を生み出すことを目的とした工事となります。空調設備の技術は日々進歩しており、省エネルギー技術も刻々と変化しています。空調機器の更新は、エネルギー効率が悪い設備を省エネ機器に転換するチャンスでもあります。機器の更新は経済性を高め、新しい価値を生み出すステップといえるのです。
更新工事のメリット
●省エネルギーの実現
●新しいスペースの創出も可能
●経済性・快適性を向上
●短期に更新を実現
●業務を続けながら実施可能
建物の竣工とともに設置された空調・電気・計装などの各種設備は、利用時問や経年変化による老朽化が避けられません。これらの設備は保守管理を徹底しても物理的な劣化は避けられず、次第に能カが低下していきます。こうした設備機器を取り替える作業が「更新」です。更新は、単に取り替えるだけでなく、将来を見据えて先進の性能を採り入れる絶好の機会でもあります。
大幅な電力の削減
建物環境の快適性を保つために欠かせない空調設備ですが、その電気量は、実に建物全体の40~50%を占めています。職場建物の急速なOA化から、電力消費はますます増大する傾向にあります。省エネルギー対策型への更新は、建物全体の電カ消費を低減する決定的な解決策ともなります。
現在、各現場の搬入スペースに合わせ現場組立型空調、コンパクト型、天吊型など、多彩な空気調和機が存在しています。OA化による室内負荷やスペースの用途変更にともなう、機器の風量・静圧・能カ変更など設計改造もよくある話となっています。
まとめ
空調設備については今回紹介した更新工事以外にもクリーニングや修理などが存在しています。状況に応じてどのような工事を行うことが最適化を考えていくことが重要になるのです。ただ、これからの時代は省エネの時代です。空調設備により省エネ化は建物の省エネを考えると避けては通れない内容であるといえます。是非空調設備を見直すことで省エネ化の実現に取り組んでいただければと思います。
『 空調機の更新ってする方がいいの!? 』
投稿日: 2019年4月15日 作成者: admin
先週は空調の自動制御について紹介をさせていただきました。空調を手動で制御するのではなく、空調自体による自動制御とすることで、人的な感覚では分からない微妙な温度の調整を行い、省エネ(電気代の削減)に繋げることができるのです。
今週のブログは先週から引き続き空調設備の自動制御について事例を交えながらご紹介していきたいと思います。是非皆さまの今後の職場環境の改善にご活用いただければと思います。

空調管理を自動制御する方法?
空調設備を人の感覚ではなく自動制御する方法についてどのようなやり方があるでしょうか?ここでは空調の自動制御について一部を事例として紹介したいと思います。
サイクリック制御
空調の自動制御の方法の1つにサイクリック制御というものがあります。これは複数の空調機がある場合に、消費電力を削減するために順次それらの空調機を制御する方法です。サイクリック制御では3分という短い時間で空調機を順次制御しますので人間の感覚では通常気付き難い範囲(1.0℃~1.7℃)でのコントロールが可能となります。
温度認識制御
又、温度認識制御というものも手段の1つとして有効です。空調機は、電気やガスのエネルギーを使用して熱交換を行っています。冷房時には室内から室外へ熱を放出し、暖房時は室外から室内へ熱を取り入れます。空調機がどれだけの運転をして、設定温度を維持するかは、外気温や建物の気密度、室内側の熱量によって随時変化していきます。それを自動制御する方法が温度認識制御となります。
例えば、室内側の熱量が増えた場合や(人が増える、発熱する物が増える等)外気温の上昇にともない、室内側への熱移動が増えた場合に空調機が交換しなければならない熱量が増えます。逆に、外気温等が下がると、熱移動は小さくなり、電気使用量も少なくなります。そして、使用環境の変化によって刻々と変化する空調機の稼働状況を電力、運転時間、温度変化量からとらえていくことで、空調機が交換した熱量、言い換えれば、壁や 窓などを通して起こった熱移動の熱量と室内側の発熱による熱量を交換したことになります。
空調機(冷凍機)は、通常設定温度に対して一定の幅を持った温度帯で運転・停止を行っています。設定温度を操作することで消費電力を抑えることは可能ですが、同じだけの温度幅を持ったまま運転・停止することになるため、その分快適性が損なわれます。例えば、設定温度を上げると温度曲線が上方にスライドするため、 高い温度帯を移行する時間が長く発生し、不快感を感じやすくなるのです。従来の設定温度時の温度帯域自体は変化せず、温度変化量は少なくさせることで快適性を維持することが重要であるといえます。
まとめ
今回ご紹介したような方法で空調設備を自動制御することは可能です。単純に設定温度を変えるのではなく人が不快に感じない温度設定
『 空調機を省エネ化するために!?② 』
投稿日: 2019年4月15日 作成者: admin
皆さまが普段使われている建物のなかには、当然空調設備が入っているかと思います。夏場の暑い時期や冬場の寒さを凌ぐためには空調は必須なのではないでしょうか?(特に昨年の夏は猛暑が続いたため空調頼りだった方も多いのではないでしょうか?)
ただ、そんな空調設備ですが「温度維持をするには電気代がバカにならない・・・。」といった不満を待たれている方もいるのではないでしょうか?
空調設備は必ず必要な反面、その維持が大変な設備であると言えます。
今回はそんな空調設備の省エネ化(電気代削減)について数週にわたってご紹介していきたいと思います。是非皆さまの職場環境改善の1つとして活かしていただければと思います。

空調管理は意外と難しい!?
設定温度を維持するには多くの電力が必要です。理想的には現場の判断で適切な空調管理をしたいのですが現実ではそれは難しいことが多くあります。現場のなかの判断では随時適切な温度を判断して空調管理をすることは実務的ではないためです。又、温度呼応速度が遅いため冷やし過ぎや暖め過ぎはどこの建物でも発生してしまいます。建物面積が大きければ尚のことではないでしょうか?制御時間や制御のタイミング、警報等では、あくまで現場担当者の判断に頼ってしまうところも多く、根本的な解決策とすることは難しいのです。
このように現場の感覚で判断をしていたのでは難しい空調管理を適切な管理することで省エネに繋げていくためには人力以外の方法が必要になります。
空調機の運転を制御する
それではどのような管理を行えば効果的な空調管理を行うことができるでしょうか?ポイントは空調機、冷凍機の運転そのものを管理していくことにあります。
空調は人の感覚で判断するのではなく、デマンド管理することで自動的に最適な温度を維持することができます。デマンド監視、自動デマンドコントロールを行うことで、空調機の運転・停止の性質を加味して電力使用量の大きな削減にも貢献することができるのです。変動する使用状況をリアルタイムで把握してこそ、最適化計画に基づいたエネルギー使用や、 CO2排出削減計画の最適化も実現することができるのです。
まとめ
このように空調管理1つをとっても様々な考え方があります。少なくとも手動で管理していたのではロスが大きいことはご理解いただけたのではないでしょうか?空調管理は如何に効率的に無駄なく行うことができるか?がポイントとなっているのです。次週は空調を自動制御するための具体的な方法を事例として紹介したいと思います。是非皆さまの空調管理にご活用いただければと思います。
『 空調機を省エネ化するために!? 』
投稿日: 2019年4月15日 作成者: admin